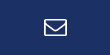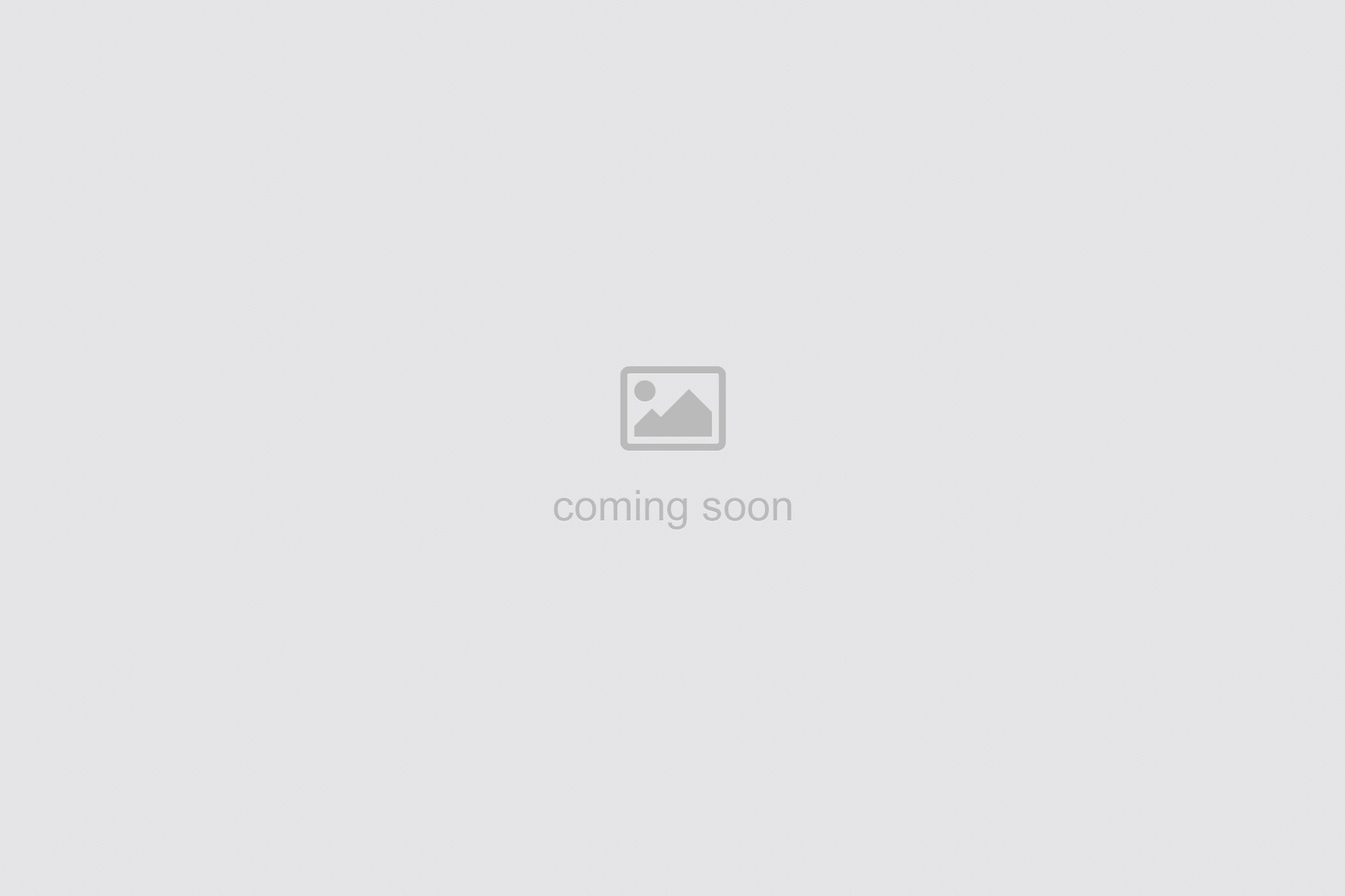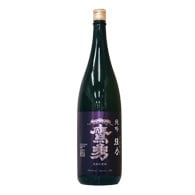ゴールデンウィーク発送のお知らせ
ご注文は2024年4月25日(木)AM8:00受付分までをゴールデンウィーク前の発送とさせていただきます。
2024年4月25日(木)AM8:00以降もご注文は受け付けいたしておりますが、 商品のお届けにつきましてはゴールデンウィーク明けより順次発送させていただきます。
ゴールデンウィーク期間は配送各社の配送量増加による混雑に伴い、やむをえず商品のお届けに遅れが生じる可能性がございます。
2024年4月25日(木)AM8:00以降もご注文は受け付けいたしておりますが、 商品のお届けにつきましてはゴールデンウィーク明けより順次発送させていただきます。
ゴールデンウィーク期間は配送各社の配送量増加による混雑に伴い、やむをえず商品のお届けに遅れが生じる可能性がございます。
また、現在新型コロナウイルスの感染拡大対策の影響により、一部地域のお荷物についてお届けに遅れが生じております。
皆さまには何かとご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
皆さまには何かとご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
私たちの思い
創業明治5年。大谷酒造株式会社は、鳥取県の中央に位置する琴浦町で150年以上の伝統を守り続けてまいりました。
大山の山麓の豊かな自然、冬の寒風、雪解け水を含んだ土地柄が酒造りに適し、加えて原材料は山田錦を基本に玉栄(タマサカエ)、鳥取県だけの酒造好適米、強力(ゴウリキ)等を使用し、一貫して米作りから酒造りまで創り手の顔が見えてくる辛口にこだわって造り続けています。
当社を代表する酒名『鷹勇』の由来は愛鳥家だった初代当主が大空を舞う鷹の勇姿に魅せられて名づけました。2007年まで杜氏を務めた坂本俊は「現代の名工」に選ばれ、黄綬褒章も受賞した名人。その後を継いだ曽田宏も「現代の名工」に選ばれ「黄綬褒章」も受賞しています。
現在は後輩の杜氏や蔵人たちにより「鷹勇」の味が脈々と受け継がれています。伝統を守りながら進取の気概を持ち新商品の開発にも積極的に取り組んでいます。
山陰地方の隠れた銘酒として非常に高い人気・評価を頂いております。今後も常にお客さまの側に立ち、感謝の心を忘れず、一意専心品質第一をモットーとして、お客さまに喜ばれるお酒を届けることに取り組んで参ります。
お知らせ
おすすめ商品
お客様の声
長谷 渉 様
松村 泰久 様
日本語ナレーション
英語語ナレーション
「とっとりの酒ツアー」大谷酒造編が公開されております。
米作りから酒造りの思いを、語らせていただきました。ぜひ、ご覧ください。
大谷酒造株式会社
代表取締役:大谷 修子が鷹勇の由縁、酒造りの想いをインタビューしていただきました。ぜひ、ご覧ください。
\SNSでも情報発信中/
お問い合わせ
ご質問やご相談など、お電話・メールにてお気軽にお寄せください。
〒689-2352 鳥取県東伯郡琴浦町浦安368
0858-53-0111 FAX:0858-53-0112
営業時間/9:00~17:00
定休日/日曜・祝日・その他(会社カレンダーによる)
- 資料請求、お問い合わせの際は「個人情報保護方針」をお読みになり、同意のうえお問い合わせください。
- 回答に時間がかかる場合があります。お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。